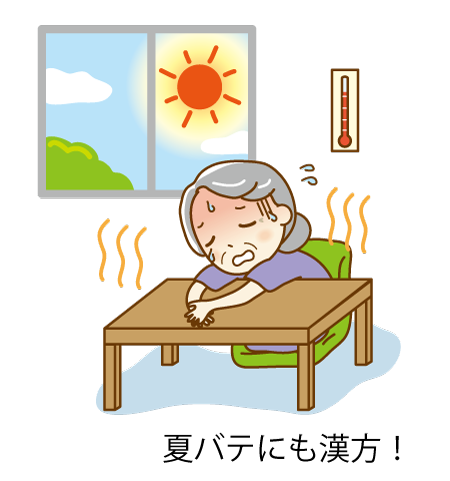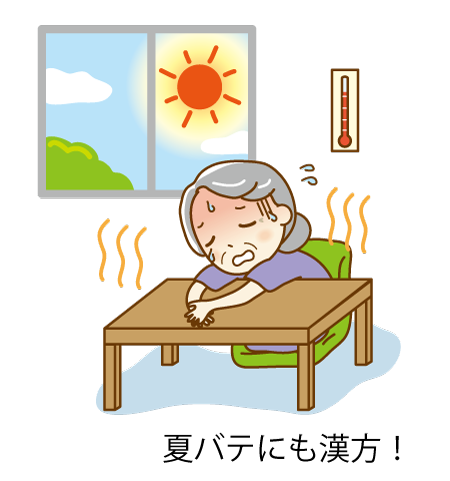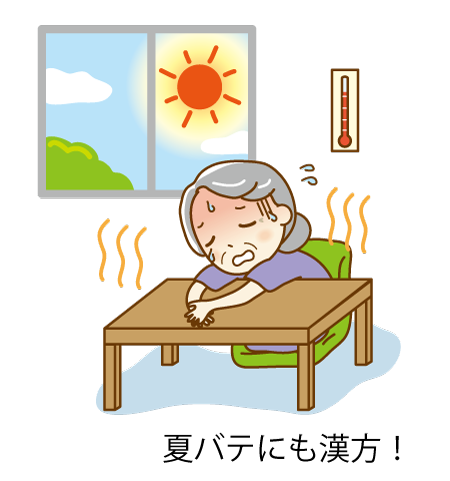
梅雨の中休みなのか連日、気温が30℃を超える日が続いています。
皆さん、体調はいかがでしょうか?また、コロナ以降マスクを手放せない人も増えているような気がします。
マスク熱中症という言葉も聞きますし、すでに熱中症で搬送されたなんてニュースも流れています。
本来夏バテは夏の暑い盛りから初秋になって体調の不調を訴えることを言っていましたが、最近は夏前から
猛暑になり体の不調を訴えるケースが増えています。
まさに今がその時期かもしれません。
症状としては、だるい、食欲がないといった症状が主に現れます。
現代では、さらに冷房による冷えも絡み合って、より複雑な病態を呈しています。
夏なのに冷え性を体感されている方もいるのではないでしょうか?
夏バテの漢方処方は、代表的にはだるさを取ってくれる補中益気湯、さらに脱水状態にも対処できる
清暑益気湯、水の偏在を治してくれる五苓散などが有名です。
①補中益気湯は、中を補い気を益す薬という意味があり、疲弊した消化吸収機能を高め元気を出す薬です。
夏バテだけではなく、消耗性疾患の基礎体力向上、自然治癒力の改善、免疫力の増強を目的に幅広く
使われるお薬で別名、医王湯とも呼ばれます。
②清暑益気湯は消化器を補い元気を益す生薬の他に人参、麦門冬、五味子という組み合せを含み、
この3つの生薬の組み合せは、生脈散と呼ばれ、暑気あたりによって脱水状態を来たした病態に
使われてきたものです。
ですから、清暑益気湯は夏専用のお薬として作られたものです。
さらに下痢止めの生薬も入っているので冷たいものの摂り過ぎによる下痢にも対応できます。
熱中症で救急搬送される患者さんのニュースも目にします。
電気代も高くなり節電も美徳かもしれませんが、健康を損なっては元も子もありません。
どんどん温暖化が進んでいますし、我慢せずにエアコンなどは活用すべきです。
それと、やはり夏には体を冷やし水分を上手に補ってくれる食事(酢の物やすいかなど)、
昔の知恵も活かしたいものです。
何かお困りのことがあればぜひ、ご相談下さい!!