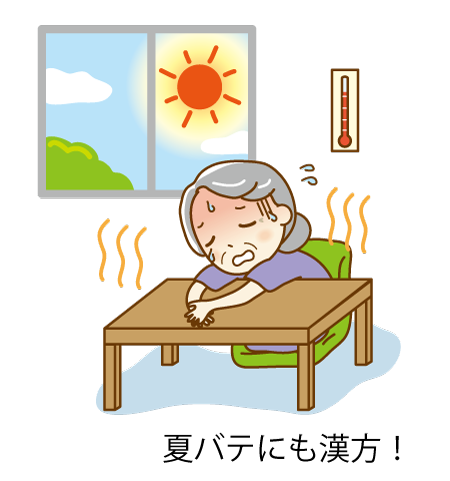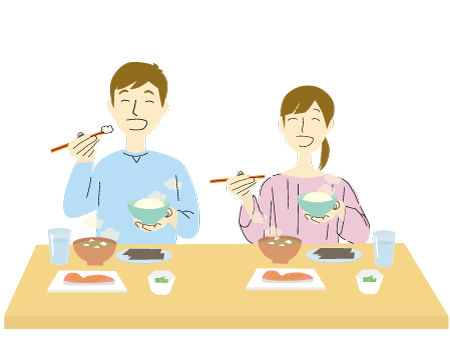ブログ
ブログ一覧
熱中症(夏バテ)対策できていますか?
梅雨の中休みなのか連日、気温が30℃を超える日が続いています。
皆さん、体調はいかがでしょうか?また、コロナ以降マスクを手放せない人も増えているような気がします。
マスク熱中症という言葉も聞きますし、すでに熱中症で搬送されたなんてニュースも流れています。
本来夏バテは夏の暑い盛りから初秋になって体調の不調を訴えることを言っていましたが、最近は夏前から
猛暑になり体の不調を訴えるケースが増えています。
まさに今がその時期かもしれません。
症状としては、だるい、食欲がないといった症状が主に現れます。
現代では、さらに冷房による冷えも絡み合って、より複雑な病態を呈しています。
夏なのに冷え性を体感されている方もいるのではないでしょうか?
夏バテの漢方処方は、代表的にはだるさを取ってくれる補中益気湯、さらに脱水状態にも対処できる
清暑益気湯、水の偏在を治してくれる五苓散などが有名です。
①補中益気湯は、中を補い気を益す薬という意味があり、疲弊した消化吸収機能を高め元気を出す薬です。
夏バテだけではなく、消耗性疾患の基礎体力向上、自然治癒力の改善、免疫力の増強を目的に幅広く
使われるお薬で別名、医王湯とも呼ばれます。
②清暑益気湯は消化器を補い元気を益す生薬の他に人参、麦門冬、五味子という組み合せを含み、
この3つの生薬の組み合せは、生脈散と呼ばれ、暑気あたりによって脱水状態を来たした病態に
使われてきたものです。
ですから、清暑益気湯は夏専用のお薬として作られたものです。
さらに下痢止めの生薬も入っているので冷たいものの摂り過ぎによる下痢にも対応できます。
熱中症で救急搬送される患者さんのニュースも目にします。
電気代も高くなり節電も美徳かもしれませんが、健康を損なっては元も子もありません。
どんどん温暖化が進んでいますし、我慢せずにエアコンなどは活用すべきです。
それと、やはり夏には体を冷やし水分を上手に補ってくれる食事(酢の物やすいかなど)、
昔の知恵も活かしたいものです。
何かお困りのことがあればぜひ、ご相談下さい!!
病は気から!!
病は気からとよく言われます。
これは漢方では、生体を維持する循環要素として、「気」、「血」、「水」といった考え方がありますが、気の乱れが血や水にも影響を及ぼすと考えられていることにも起因しています。
気とは、生命活動を営む根源的なエネルギーと解されています。
しかし目に見えないものですから、未だにその理解が進んでいません。
気の病には次の3つのタイプがあります。
| 分類 | 病態 | 主要な症状 | 治療法:生薬例 |
| 気虚 | 量的不足 | 倦怠感・易疲労・食欲不振 | 補気:人参、黄耆 |
| 気鬱 | 循環障害・停滞 | 抑うつ・閉塞感・異物感 | 順気:厚朴、紫蘇葉 |
| 気逆 | 循環障害・逆流 | のぼせ・動悸・不安 | 順気:桂枝、黄連 |
現代医学では診断のつかない症状でも、気のせいじゃありません。
漢方では病名がつくのです。そして治療薬も用意されています。
| 分類 | 代表的な治療薬 |
| 気虚 | 六君子湯、 人参湯、 補中益気湯 |
| 気鬱 | 香蘇散、 半夏厚朴湯、 女神散 |
| 気逆 | 苓桂朮甘湯、 桂枝加竜骨牡蛎湯、 桃核承気湯 |
五月病とは新しい環境に適応できないことに起因する精神的な症状の総称として使われている言葉です。
専門医の間では、スチューデントアパシー(学生の無気力症)、サラリーマンアパシー(サラリーマンの無気力症)などと呼ばれています。
また医学的には適応障害とも言われますが、これも気の病のひとつです。
受験、入学、転校、入社、転勤と春は環境変化によるストレスの多い季節でもあります。
またストレスは現代病のひとつでもあって、最近ではフェイスブックなど流行の最先端のものまで私たちはストレスの負荷を受けていたりするのです。
補気はほとんど中焦(脾胃)の機能を整え活気付ける方剤です。
つまり気の不足は食事から補うとも考えられています。
ちゃんと朝食を取っていますか?
暴飲暴食を避け、過度なダイエットを慎み、1日3回規則正しい食事を取ることをお勧めします。
R7.5.17ブログ
これまでに何度も地域包括ケアシステムやつづ∞つなについてお知らせさせていただきましたが、こうした取り組みをしていると本当に様々に地域のことを考え、マイノリティーの方々に対しての取り組みも様々です。
つづ∞つなの取り組みはそうした方々をつなげるために始めましたが、つづ∞つなよりもつながりを構築し成長されている多くの取り組みを見て感心し、そうした団体、組織とうまく連携し活性化していければと期待できる状況です。
しかしながら広島県は人口流出ワースト1位を4年連続、その中で呉市は人口流出県内市町村でワースト1位です。
人口の多い広島、福山、東広島は減るどころか増えています。
すなわち呉市は待ったなしで対策が必要であり、対策を遂行しなければ地域包括ケアシステムは衰退し、住みにくい街になり益々人口流出、呉市に住みたい人も減っていくということです。
様々に住みやすく、活気が戻る対策が必要ですが、その中でも日新製鋼跡地、呉駅前再開発、そして地域医療構想が今後を左右する大きな取り組みになると思っています。
これは行政だけに任せるのではなく、市民一人一人が意識を高めて協力、支援、参加していくことが大切だと思います。
なので是非ともつづ∞つなへの参加をお待ちしております。
不眠症に用いる漢方薬
皆さん、よく眠れていますか?
今回は不眠症に使われる漢方薬についてお話します。
不眠をタイプ別に分類すると、入眠障害(寝つきが悪い)、熟眠障害(眠っているけどよく眠れた感じがしない)、中途覚醒(しばしば目が覚めてしまう)、早朝覚醒(早く目覚めてしまう)に分けられます。
食う、寝る、出すというのは人が健康に生活していくうえで非常には大事なことだと思います。
睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠があることを聞かれた方もいるのではないでしょうか?
浅い眠りをレム睡眠、深い眠りをノンレム睡眠といいます。
今、特に高齢者の睡眠障害が増えていると言われています。
その特徴はノンレム睡眠には4段階あるのですが、より深い眠りの第3,4段階の眠りが減少しているということが分ってきています。
つまり浅い眠りの段階が増え、中途覚醒の回数と時間が増えているということです。
不眠に対する漢方薬の代表は、まず酸棗仁湯(さんそうにんとう)が挙げられます。
2000年前の古医書「金匱要略(きんきようりゃく)」に登場する薬です。
条文には「虚労、虚煩、不得眠、酸棗仁湯主之」(虚労(きょろう)、虚煩(きょはん)、眠ることを得ざるは、酸棗仁湯(さんそうにんとう)之(これ)を主(つかさど)る)とあります。
常に疲れて弱って、些細なことが気になって眠れないものを治すということです。
酸棗仁湯に含まれる酸棗仁(さんそうにん)という生薬は不眠だけではなく、眠り過ぎにも有効で、睡眠異常の正常化薬だといわれています。
ほかには、イライラ感があって眠れないというものに、柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)や抑肝散(よくかんさん)、柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)、加味帰脾湯(かみきひとう)など柴胡(さいこ)という生薬の入ったものもよく用いられます。
柴胡には肝(疳)の昂りを鎮める作用があります。
柴胡加竜骨牡蛎湯や桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)に含まれる、竜骨(大型哺乳動物の骨の化石)や牡蛎(かきの殻)は、ともに主成分は炭酸カルシウムで精神安定作用を目的に加えられた生薬です。
恐い夢を見るとか、物事に驚きやすいといった症状が使う目標になってきます。
悪夢に効く漢方薬があるわけですね。
漢方薬はいずれも直接的な催眠剤ではないので、眠前投与とは限らず、1日3回服用も標準的な使い方です。
ハングオーバー(薬の持ち越し効果)や脱力感、薬物依存などの心配もありません。
日常生活に悪影響がないだけではなく、全身的な体調も整えてくれます。
尚、米国の調査では健康な人の睡眠時間は6~7時間だとする疫学データも出ています。
つまり眠り過ぎも良くないということです。
大事なのは時間ではなく、睡眠の質ということですね。
R7.4.17ブログ
これまで多くの言葉をたつき新聞や職員、剣道教室の子供たちなど様々に伝えてきました。
そして私自身自法人が、携わる会や地域が少しでもよくなるためには何が出来るか、何をすべきか考え実行してきました。
何度もお伝えしてきた言葉も多くありますが、その中でももっとも伝えてきたのは自分で限界を作ったら、そこで成長は終わると…
しかしながら様々に取り組む中で私も人間であり、限界を感じる、心身が持たないと感じることは何度も感じてきました。
そんな時にしてきたことは優先順位を考えることで、優先順位が低いものは延期または中止します。
中途半端に続けるとすべてが中途半端になり、頭もまとまらなくなるからです。
正直余裕ができて再度始めたことはほとんどないと思います。
人は時間があれば無駄に時間を費やすことが多くなると思いますし、時間が無ければ切り詰めて時間を有効活用します。
そしてどこかに少しに余裕を持ちながら全力で取り組んできたのかなと思います。
ここで一つお伝えしたいことは、そんな中でも優先順位、すなわち大事なこと、必要なことは絶対にあきらめないという事です。
もっと言えば心身に負担が大きくなればどうすればそれを回避し大事なことを続けられるかを考えてきました。
それが結果的には地域や職場、そして人間関係を構築していけると信じてやってきましたし、そのために今ある問題点を解決すべく周りを巻き込んで取り組んできました。
地域に必要とされるたつき会を構築し、地域で永続する組織を造り上げるために取り組んできましたが、容易ではありません。
今、一大プロジェクトを立ち上げようと考えておりますが、人財なくして実現せず困難な状況です。
それでもめげずに最後の地域貢献に取り組んでみようと思っております。
うまくいけば次代の人たちが繋いでくれると思います。
うまくいかなければ地域貢献の組織を続けることが難しくなるのだろうと思います。
当法人が発展し、地域貢献できる組織になるように職員はもちろん、多くの方々にご支援を頂ければと願います。