ブログ
ブログ一覧
R5.2.11ブログ
今年から再出発したブログですが、「たつき会の地域包括ケアシステム」として発信しております。
今回は今年の8つの目標の中の一つである「地域包括ケアシステムの発展」を深堀りしたいと思います。
繰り返しになりますが、地域包括ケアシステムとは住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るように、地域で医療・介護・住まいなどを一体的に提供するシステムのことです。
医療や介護を受けることから、医療・介護分野から発信された言葉であるため、医療や介護に携わる方々は医療と介護を中心に考えられることが通例です。
しかしながら私はこの言葉が使われ始めた当初から「生活」に着目していました。地域の方々に「生活」無くして医療も介護もありません。それは当然のことと思われますが、医療や介護分野で働く方々にも、当然「生活」があってこそ仕事が出来ます。
さらに医療や介護事業所は職員が従事しているから成り立つのは当然ながら、医療や介護に必要な医薬品や生活必需品が手に入らなければ日々の運営は成り立ちません。
例えば入居施設で散髪をしたくても施設へ訪問してくれる理容業の方が居なければ素人が対応するしかありませんし、オムツや食料品が調達できなければ冷凍やレトルトなどの食品になります。介護サービスには送迎もありますので給油所や車の整備工場も地域に無いと困ります。職員に子供がいれば学校・教育に関わる場所も必要です。
結局「生活」に必要なものが地域に無ければ不自由で自分らしい最後は迎えられないと言うことです。
なので私は地域の他職種がつながるために様々な取り組みを開始したのですが、軌道に乗り始めたと思ったところで、コロナ禍に突入し頓挫してしまいました。様々な方法はあったのですが、コロナ対応に追われ、結果何もできず3年が経過しました。
そこでこのたび地域包括ケアシステム構築のために、法人内で担当職員を任命し再始動しております。現在地域の方々と打ち合わせをしながら方向性を定め、実際に「けん玉教室」などで地域に出向き活動をしてくれています。知っている人は知っているかと思います。
しかしながらこうした活動は容易なものではありません。右往左往することもあるでしょう。
ただ地域包括ケアシステム、地域のつながりが大事だということはご理解いただけるものと思います。
少しでも早く、少しでも良いものにするためには一人ひとりの協力と参加が必要となりますので、会合などを企画した際は是非ともご支援、ご参加お願いします。

しもやけに効果の期待できる漢方薬!!
まだまだ寒い日が続いていますが、最近は冬の季節ならではの『しもやけ』でお困りの患者さんが多く見受けられます。来院されずとも、毎年しもやけによる痛みや痒みで困っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。特に女性は家事で水に触れる機会が多くなるので、ハンドクリームを塗ってもあまり意味がないと感じられているのではないでしょうか…?
そんな辛い悩みの解決が期待できる漢方薬ご存じですか?しもやけの辛い悩みを今年で最後にしませんか?次の漢方薬を使うと、その悩みが解消されるかもしれません!
そんな魔法のような漢方薬は
当帰四逆加呉茱萸生姜湯
(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)
といいます。
呪文のようなとても長い名前です。恐らく医療用の漢方製剤の中でも一番長い名前ではないでしょうか。この漢方薬は、『四肢末梢の冷えが強く体調を崩しやすい方で、不定の疼痛を訴える場合に良い』、いわゆる『冷え症』に用います。
★ポイント:西洋医学では ‘冷え性(自覚症状や体質を指す)’として治療対象としないことが多いのですが、漢方医学では ‘冷え症(ひとつの病気)’として重視します。
当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)
は10個の生薬から構成されますが、主な役割は次のとおりです。
| 桂皮(けいひ)、呉茱萸(ごしゅゆ)、 細辛 (さいしん) | 温め、温かさを全身に巡らせる。 |
| 芍薬(しゃくやく)、当帰(とうき) | 血行を良くして末梢の冷えを改善する。 |
桂枝湯(けいしとう)という上手に身体を温めることができない虚弱な方にも対応できる漢方薬がベースになっています。
当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう) は、
① 服用後、30分くらいで手足が温まる
② 予防的に使えば次の年にしもやけが見られないといったようなデータもあるので、お困りの患者さんは是非、ご相談ください。
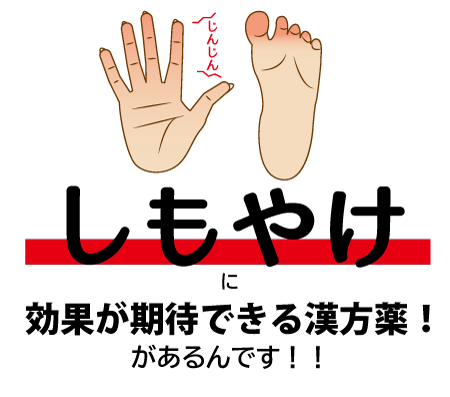
R5.1.11ブログ
新年を迎え今年新たな目標を少しでも実現していくために、個人的な記事ではなく、地域や市民の方々にお役に立てる情報発信や当法人の取り組みを紹介することで安心をお届けできるよう、目的を持った内容で「たつき会と地域包括ケアシステム」としてお送りしたいと思います。
このたびは今年の目標について具体的にどのように取り組んでいくかなどお伝えしたいと思います。
①コロナ禍で永続できる感染対策作り
→これまで当法人で様々に取り組んできた対策の中で効果的であったことを具体的にお伝えしていく
②法人内のコミュニケーション向上
→コロナ禍で職員間のコミュニケーションが不足しがちの中、どんなコミュニケーション方法が可能になったかをお伝えしていく
③法人内外システムの充実
→これまで法人内で取り組み効果的であったことは勿論、今後地域との連携を行うために取り組むことをお伝えしていく
④地域奉仕活動の充実
→コロナ禍でも様々な活動が行われるようになってきた現在、感染対策を行いつつどう地域活動に参加していくかをお伝えしていく
⑤安心して働ける職場創り
→法制度を利用しながら、介護や子育てと仕事を両立でき安心して働ける職場環境を整える取り組みを具体的にお伝えする
⑥利用者が楽しく生活できる取り組み
→当法人が取り組むDCT(夢をかなえる)活動を具体的にお知らせする
⑦BCP(事業継続計画)の充実
→災害に備え当法人が準備した内容を具体的にお伝えし、地域に少しでも安心を提供する
⑧地域包括ケアシステムの発展
→これまで「樹立の会」や「川安の集い」など行ってきたが、コロナ禍でストップしたままになっている。上記の目標を実行することも発展につながり、さらには多職種で地域を守ることが本来の地域包括ケアシステムであるということを一人でも多くの方に理解していただき、協力を得ていけるよう情報の発信をおこなう
地域の状況が軽傷であれば費用が安く簡単に治りますが、重症となれば費用がかさみ難治で、最悪滅びてしまいます。
私は10年以上前からそうした危機感を持って取り組んできましたが、危機感のない方が多いのが実情かと思いますし、他人ごとになっている方も多いと感じます。
何が危機なのかも含め、ブログでお伝えすることで理解して下さる方が増え、協力団結して行けることを夢見て取り組もうと思います。
本年もどうぞよろしくお願いします。
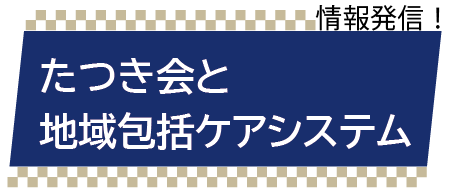
身体を温める生薬、附子(ぶし)と乾姜(かんきょう)について
西洋医学では冷えに対して確立した治療法はありません。せいぜい下肢末梢の知覚障害、血行障害、運動障害がないことをチェックするくらいです。大半の場合は(特に若い女性では)、西洋医学的治療の対象を見出せず、漢方の助けを借りることが多くなります。
漢方医学的な病態(証)の基本的な分類は『陰証』と『陽証』です。陰証は生体の反応力が低下した病態で、体温産生も不十分なため“冷え性”になりがちです。漢方医学的には冷えを『寒』といいます。
さて実際の冷え症状は、全身型、上熱下寒型、末梢循環不全型と大きく三つに分類して治療方針を考えます。「全身型」は、全身的に寒が支配する真性の寒で、陰証の冷えです。治療は服用することで生体を温める熱薬(附子や乾姜など)を含む方剤を用います。
附子はトリカブトの根を減毒処理したもので、バーナーで燃やすように強く体を温める作用や鎮痛作用があります。乾姜はショウガを蒸して乾燥させたもので体の中(裏)から温め、元気をつける(補気)作用が強いものです。この二大熱薬である乾姜と附子に甘草を加えた方剤を四逆湯といい、温める漢方薬の基本骨格となっています。尚、四逆湯はエキスにはありません。名前が似ていますが四逆散(ツムラ35)は全く別の薬なので注意が必要ですね。

漢方薬のおいしい飲み方 ~子ども編~
『良薬は口に苦し』
漢方薬ほどこの言葉が似合う薬はないと思います。とはいっても、そんな理由で子どもが苦くておいしくない薬を飲んでくれるか?といえば、それは難しいことでしょう。しかし、美味しく飲む方法が実はあるんです!
今回はその飲ませ方の工夫を紹介します。
まずは薬に対して子どもがどのような反応をするか、年代別に知っておきましょう。
| 乳児期(0~1歳) | 比較的飲ませやすい |
| 幼児期(2~5歳) | 薬に敏感で、しばしば服薬拒否 |
| 学童期(6歳以降) | 漢方の必要性を理解すれば比較的飲ませやすい |
漢方を飲ませるのが難しい年代は幼児期です。この間に苦い漢方薬に慣れていくと、もしかしたら食べ物の好き嫌いがない子どもに育っていくかもしれないですね。
では、肝心の『漢方の飲ませ方』について見ていきたいと思います。
①甘い漢方薬を飲ませてみる
漢方薬に苦手意識がある子どもには甘い漢方薬から飲ませてみましょう。
比較的飲みやすい漢方薬は、建中(けんちゅう)湯類(とうるい)(黄耆建中湯(おう ぎけんちゅうとう)、小建中湯(しょうけんちゅうとう))、甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)、芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)、麻黄湯(まおうとう)、六君子湯(りっくんしとう)、桔梗湯(ききょうとう)があります。
②味付けをしてみる
1回分の漢方薬を適量のお湯に溶かして溶液を作ります。そして砂糖やココア、麦芽飲料、ハチミツ、アイスクリーム、ヨーグルトなどに混ぜて下さい。ただ、ハチミツにはボツリヌス菌が含まれている可能性があるので、乳児には与えないように。ココアや抹茶コーヒーなど少し苦めの味のものと混ぜ合わせると、味と香りが相殺されて飲みやすくなったりします。アイスクリームやヨーグルトなどの冷たいものは味覚を鈍くさせて苦みをわかりにくくする効果があります。しかし、胃腸が弱っていたり、風邪の引き始めで悪寒がしている時などには温かいものに溶かして飲ませたほうが効果も増強します。
いかがでしたか?
是非試して、子どもが笑顔いっぱいで飲めるようになってもらいたいですね。

