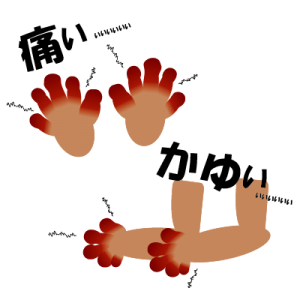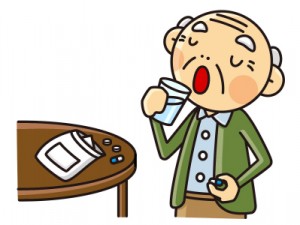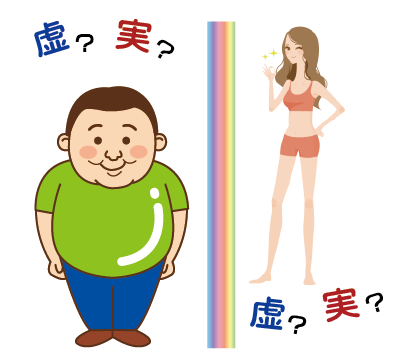超高齢化社会が叫ばれる中、嚥下障害、誤嚥性肺炎を起こす患者さんは年々増えています。
 食べる楽しみが障害されるということは大変ショックなことと想像に難くないのですが、漢方ではその「食べる」ということを非常に重視しています。それは食べることが元気の「気」の源だと考えているからです。
ですから元々は、「気」という字は「氣」と表わしていたのです。
食べる楽しみが障害されるということは大変ショックなことと想像に難くないのですが、漢方ではその「食べる」ということを非常に重視しています。それは食べることが元気の「気」の源だと考えているからです。
ですから元々は、「気」という字は「氣」と表わしていたのです。
食べられるようにするには、六君子湯や補中益気湯が有名です。
さて、嚥下障害・誤嚥性肺炎に対する漢方薬は、日本老年医学会診療ガイドライン指針案にも推奨されていた半夏厚朴湯です。
原典ではおよそ2000年前の書籍「金匱要略」に、「婦人、咽中炙臠有るが如く、半夏厚朴湯、之を主る」とあります。
つまり、咽喉頭異常感症に対する治療薬として昔から使われてきたものです。
また、咽喉が塞がる感じだけでなく、気分が塞ぎ、不安感や憂鬱間のある時や、咳、吐気に対しても有効な薬です。構成生薬は、半夏、茯苓、厚朴、蘇葉、生姜の5つです。生姜、半夏、茯苓の組み合わせは悪阻にも使われる小半夏加茯苓湯そのものです。また小柴胡湯を合せた柴朴湯は喘息にも有用です。
他に嚥下反射を改善する薬としては、ACE阻害薬、ドパミン作動薬(アマンタジン)、抗血小板薬(シロスタゾール)などがあります。
しかしそれだけでは良くならない方もいらっしゃいます。
胃食道逆流が原因の場合には、半夏厚朴湯に茯苓飲を合せた茯苓飲合半夏厚朴湯や、半夏厚朴湯に六君子湯を併用する必要があります。また腸管ガスが充満し、便秘も酷く、食物が下に輸送されず逆流が起きる場合は大建中湯の併用が必要です。
実際、誤嚥性肺炎の患者さんの胸部単純X線写真を見ますと、ほとんどのケースで横隔膜下に異常ガス像を伴っています。
更に誤嚥性肺炎を繰り返し、高熱の出る場合には、抗菌薬とともに清肺湯も良く用いられる漢方薬です。
ところで、そもそも嚥下反射が低下した患者さんに漢方薬を飲ませる時どうすればいいかという問題があります。
ゼリー、ヨーグルト、ペースト食に混ぜる、お湯に溶いた後、トロミ剤を混ぜる、その他患者さんが口にできるものに混ぜるなどといった工夫が必要です。
尚、このような場合は、当然ながら、食前または食間といった指示にはこだわることはありません。
寝たきりで経管栄養から離脱し、最期まで食を楽しみ、人間らしく生きたいものです。